「……」
「だって、あっちのみんなはアレが私の偽物だってこと気が付かなかったんだよ? 一度も」
「……」
「マシュでさえちょっと違和感があった、くらいだって言ってたし。
まあ、認識阻害が出てて……って説明はされたけど、それにしたってさ……」
「……」
「……ねえ。ダ・ヴィンチちゃん。どうしたの」
「……。……うん?」
「さっきからずっと考え込んでるみたいだけど。なんか変なこと言った?」
「あ、いや。こっちの話だよ。続けてくれ給え」
「あとの概要は報告済み。無事に微小特異点を修復して、聖杯を二つもゲット。それからカルデアに帰ってきました」
「うんうん。本当にお疲れ様、マスター君」
今年もいい夏の思い出ができたみたいだね、とダ・ヴィンチちゃんは手元の電子機器になにやらさらさらと書き込んだ。
カルデアに帰還した今、この医務室で行っているのは正式な結果報告というより、レイシフト後の健康観察を兼ねた、軽い雑談のような物。
「でも凄いね。男女が入れ替わってても気にならないなんて」
人類最後のマスター。『カルデアのマスター』はひとりしか存在しない。私以外に『カルデアのマスター』が存在するはずがない。
だというのに皆に顔どころか、性別さえ曖昧に覚えられていたという事実がショックだった。
そんなに印象に残らないのだろうか。代わり映えしない顔だけど、男か女かくらい覚えててくれたっていいのでは。
「我々としてもそこは盲点だったよ。まさか同時に二人存在するとは」
ため息を吐く私をよそに、ダ・ヴィンチちゃんは小難しい顔で画面を見つめている。
「……区別が付く程度まで認識阻害の度合いを緩めるべきか……でも個々に対する処理が……」
「?」
「ごめん。別件の話だよ」
もう戻って大丈夫、とダ・ヴィンチちゃんはにっこりする。
「薬、飲むのを忘れないようにね」
効能は教えられていない。いつから飲み始めたかも覚えていない。勝手にビタミン剤だと思っている。
だけど……ノウム・カルデアに来る前は、こんなの飲んでたっけ? それともシオンから提供された技術の賜物なのか。
洗面台にコップを置く。眩い照明の下、鏡に映る顔の色は悪い。熱があるみたいだ。
背後でノックの音がした。
「ああ、マシュ」
「お疲れ様です、先輩」
「どうかした?」
「いえ、あの……夏の微小特異点でのことを、ちゃんと謝りたいと思いまして」
「仕方ないよ。認識阻害が掛かってたんでしょ?」
「いいえ。違和感に気付くべきでした。いつも先輩の側に居るというのに、私は……」
真面目なマシュらしい心配だ。他の皆は夏だのホラーだのに浮かれていて、マスターの性別が変わっていたことにも気付いていなかったのに。
「大丈夫。気にしてないよ」
肩を叩く。俯いていたマシュが顔を上げて……ぐっと何かを堪える表情になった。
「え?」
「実は、私が徐福さんが化けていた方がおかしい、と感じたのは……以前からあった違和感が無くなって、顔がはっきりと認識できたからなのです」
マシュはおかしなことを言いだした。ホラーな特異点の影響をまだ引き摺っているのだろうか。
「前からなんです。マスターの顔が、分からない。あなたが私の先輩で、守るべき『カルデアのマスター』だということは事実です。でも、先輩の顔はよく見えないんです。どんなに目を凝らしても、ぼやけてしまって」
ささいな違和感をずっと抱えてきたのだろう。途中で何度も言葉を詰まらせそうになりながら、マシュは一気に思いを吐き出す。
マシュには、私の顔が見えていない。本物かどうかさえ疑うほどに。
それじゃまるで、カルデアの中でも認識阻害が掛けられているみたいじゃないか。
そんな訳ない、と言おうとして気が付いた。認識阻害が二重に掛かっていた状態だったから、サーヴァントの皆も偽者に気が付かなかったんじゃないのか?
不安になった。みんなも、マシュも私の顔が分からないなら、何を以って、今の私が本物だと証明してくれるんだろう。
疑う余地もないくらいに当たり前のことを、自分に言い聞かせる。
「そうですよね。すみません、取り乱してしまって」
「やっぱり疲れてるんだよ。今日くらいはゆっくり休んだ方がいい」
「……はい。お騒がせしました、先輩」
おやすみなさい、と頭を下げたマシュが遠ざかっていく。……会話中、一度も目が合うことは無かった。
ふらふらと部屋のベッドに倒れ込む。なんだか寒気がしてきた。
自分は自分だ。それ以外ありえない。きっと徐福の偽者を見たせいで、そんな可能性もあるのかと考えてしまっただけだ。
私が他にもたくさん存在するんじゃないかなんて、そんなこと。
いよいよ寒気が凄いことになってきた。膝を抱いてかたかた震えながら、咳き込む。口の中に広がる錆の味。ころりと舌の上を転がる硬い何か。
「……あえ?」
掌の上に吐き出す。目にも鮮やかな血と、抜けた奥歯の白が絶望的なまでのコントラストを放っていた。
向かう先は医務室ではなく、ダ・ヴィンチちゃんのラボ。これはサーヴァント達に知られてはならないことだという、直感があった。
「ダ・ヴィンチちゃん」
自動扉が開くのを待ってられなくて押し開く。椅子に優雅に座っていた少女は、待ちかねていたように顔を上げた。
「いらっしゃいマスター君。そろそろ来る頃だと思っていたよ」
「え?」
「期限が近いな。レイシフト中は薬が飲めないから、一気にガタが来たか。身体、辛いだろう? ほら、ここのベッドに横になって」
頷いて、歩こうとしたら激しく咳き込んだ。再びの吐血。ラボの床に血だまりが広がる。
怖い。私の身体が、急速に壊れていく。どうして。
思わず座り込んで歩けなくなった私を、ダ・ヴィンチちゃんが支えてくれた。覚束ない足取りで手術台みたいなベッドに横たわる。
隣にも同じようなベッドがあった。その上に載った人の顔を見て、私はひゅっと息を呑む。
「なん、で」
私だった。死に掛けている私の隣で、呑気な寝顔で別の私が眠っている。
「……君の原典(オリジナル)に当たる人物は、死んだんだ。その前に、我々の計画に同意を残してくれていた」
「けい、かく」
「『カルデアのマスター』が道半ばで倒れることは、あってはならない、ってね。人倫に悖るこの行為を、君は仕方ないと許容した」
透明な液体を注射器で吸い上げながら、ダ・ヴィンチちゃんは言う。
「君の複製を作って、死亡するたびに記録と記憶を移行して。『カルデアのマスター』という概念を続ける選択をした。完璧な複製ではないから、違和感がないように認識阻害も掛けて」
まさかそれがあの特異点で徒になるとはね。なんでもないようにダ・ヴィンチちゃんは言う。
それが事実だとしたら、この私は偽者なの? もう本当の私じゃないの?
血の泡を吐く私の腕に、ゴム管が巻き付けられた。
「安心して。死ぬわけじゃないさ」
浮き上がった静脈に、針が突き刺さる。
「……君はまた、ここで目が覚めるんだから」
冷たい薬剤が血管に染みていく。
次に目覚めるのは、今の私ではなく隣の私。
最後に告げられたこの事実も忘れて、私はきっと私らしく振舞うことだろう。
意識が白く濁り始める。一体いくつの私が、こんな風に犠牲になっていったのか、と考える余地もなく私は眠る。
また『カルデアのマスター』として、目覚めるために。
ノウム・カルデアに囚われた女の話
あの人の技術再現は無理かな…
オオオ
イイイ
憎む前に死んでリセットだから終わらない…
ここまでやるとなるととっくに話通ってんじゃねぇかな
でもまた特異点とか出るかもしれないし保存しとくね・・・
やっぱりこのぐだ子は偽物で本物の最後のマスターであるぐだおがどこかで見てました!とかじゃなくて…
心当たり多すぎるけど
記憶や意識が移されるとエドモンも移っていくとか
全部知ってて途中で不具合があった時の調整役とか
オリジナルが頼めば無下にはしないだろう
本来はその度に死んでてもおかしくないよな…
肉体魂精神の三要素があってそれぞれの要素要素ならコピーなり適切な魔術なりで引き継げなくもないけど完全に全部同じはありえない
橙子はどう説明するの
……第三魔法?
まあ普通にこういうルートもありうるよなぁ
維持の手間かけないと死ぬらしいので帰ってきても長くは…
わるいノウム・カルデアと永続させられるマスターの概念と地獄の片棒を担いで曇るアルジュナの話です
伊藤計劃いいよね…
悪い夢なら、早く覚めてほしい。
マスターの亡骸と共に、帰還した私たちを待っていたのはレオナルド・ダ・ヴィンチ。
モニター越しに起こった全てを見ていたであろう彼女の表情は、暗く強張っていた。
「……ひとまず、君たちの無事の帰還を喜ぼう。それと……」
一旦言葉を切ったダ・ヴィンチが、ふと私が抱えるマスターに視線を向ける。死後硬直が始まっていた。目蓋は閉じ切らず、薄く開いた目が、私を虚ろに見上げている。
「……マスター君を、連れて帰って来てくれてありがとう」
「――いえ」
思わぬ労いの言葉に目を伏せた。今の私にその価値はない。
いっそ無能と罵られた方がどれほど気楽だったか。本来守るべきあの人の命を殺めたことを、責められた方がどれほど嬉しかったか。
「マスター君を、こっちに渡してもらえるかい?」
「……はい」
これが最後だ。名残惜しくなって頬に触れる。傷だらけで血だらけの身体に、柔らかさなどどこにもない。冷え始めた皮膚。固まり始めた関節。もう少し放置すれば、死臭さえ漂ってくるはず。
あの人の死体は、どう扱われるのだろう。この漂白されたどこかの大地に埋められてしまうのだろうか。
たった一人で。誰も訪れることのない最後の墓標として、あの青と白の原野に。
「今まで、お疲れ様。マスター君。……どうか、束の間の夢を」
受け取ったダ・ヴィンチは慈母のような微笑みを浮かべ、血で固まったままの髪を撫でた。
「ネモ・ナース。手順通りにマスター君を」
「了解」
「マシュ。君は医務室へ。いつものバイタルチェックとそれから……」
「いいえ。……いいえ! 私のことなんていいんです!」
帰還から今まで一言も発さず、唇を噛み締め押し黙っていたマシュ・キリエライトが初めて悲痛な声を上げた。
淡い色の瞳を潤ませつつ、それでも涙を零すまいと堪えている。
「お願いです、ダ・ヴィンチちゃん。せめて、せめて最期までマスターと一緒に居させてください!」
当然の望みだ。我々は救えなかった。我々は失敗した。
マスターと言う唯一無二の希望の灯はすでに消え去り、ならばこの世界はやがて終わるのだろう。
世界の終末を大切な人の傍で。それは人らしい上等な願いのように思えた。
それでもダ・ヴィンチは首を振り、
「いいや。ちゃんと医務室で治療を受けてほしい。シオンが担当してくれるはずだ」
「ですが!」
「大丈夫だよ。心配しないでくれ、マシュ」
「……え?」
「マスター君にはまた会えるから」
慰めの言葉のつもりなのだろうか。少なくとも正にその人を喪い傷心のマシュ・キリエライトに掛けるものではあるまい。
「それは、どういうことです。どういう意味ですか!」
「ダ・ヴィンチ、それは……」
ある意味常の彼女らしからぬ言葉選びに唖然として、そこでようやく気付く。
ダ・ヴィンチの瞳が決意の色に爛々と輝いていることに。
「ともかく、治療を受けておいで、マシュ。……それと、アルジュナ」
渦巻くのは狂気だ。
「君は私と一緒に付いて来て欲しい」
底知れない深淵を覗かせる闇。そう形容する他ない青の瞳が、私を見た。
「カルデアだって、こういう事態……マスターの死を一度も想定したことがない訳じゃないんだ」
魔術によって隠されていた扉を抜け、示された先は地下へと向かう螺旋階段。
ノウム・カルデアにこんな施設があるとは知らなかった。
どこからか立ち込めた白い霧が、長く続く階段の先を覆い隠している。
「むしろ最初なんて私……いや、レオナルド・ダ・ヴィンチはマスター君が人理修復を完遂できるとは思っていなかった。五体満足なんて絶対に無理。最低どこかしらの機能は失うだろうと見込んでた」
一段一段、降りるごとに冷気が這い登ってくる。
嫌な予感がした。ここまで徹底的に隠蔽された場所。カルデア所属のマシュ・キリエライトでさえ立ち入れない施設。
それは、カルデアが正義を謳うには不都合な、悍ましい事実が隠されているのではないか。
「……」
分かっていたとしても、マスターを失った……正確に言おう、マスターを殺した私には拒否する権利などない。
導かれるままもう戻れない泥沼の底へ。地の獄へと降りていく。
「けれど、全ての特異点を修復し、見事人理修復を成し遂げ帰還した時……気が付いた。経験、思考、意志。マスター君を構成するそのすべてが、二度と得られぬ天祐なのだと」
何処までも続くかと思えたノウム・カルデアの地下深く。灰色一色の床と壁の中、寒気立つほど白い扉がそこにはあった。
「さあ、入り給え。尊き白き英雄よ」
どこか芝居がかった所作で、少女は扉を開く。
「お見せしよう。我々の罪科を」
暗い部屋に照明が灯る。医務室に似たその中を見回して……息を呑んだ。
無機質な手術台の上に載せられているのは。
「――何故」
マスターだ。まぎれもなく。
先程、確かに私が殺したはずのあの人が、横たわっている。
「起動準備、できてるかな」
声に反応したのか、あの人の目蓋が震えて、開く。歓喜とも恐怖とも悍ましさとも取れる感情が胸を掻きむしる。
口を開かないでほしい。あの人そのものの声がもう一度聞こえたなら、私の正気が保てない。
願いも虚しく、どこか懐かしささえ感じる声が私の耳を侵す。
「あ、れ。ここは……」
「ああ、良かった。目が覚めたんだね」
「……からだ、だるい」
「そりゃあそうさ。まさしく生死を彷徨っていたんだから」
「……あれ、そこ誰かが……」
首をゆっくりともたげたあの人の目が、私を見た。眩い照明の中浮かぶ白い顔は。ああ。どうしようもなく、あの人そのもので。
「……なんだ。アルジュナか」
「無理しちゃいけないよ、マスター君」
酷い大怪我をしたんだ。もう少し眠るといい。
穏やかな語りに眠気を誘われたのか、あの人の目蓋は再び閉じられた。やがて規則的な寝息が聞こえてくる。
眠るあの人の表情は安らかで、今まで見てきた全てが悪い夢だったような心地になる。
けれどこの手は覚えている。あの人の喉を裂いた感触も。吹き出る血の生暖かさも。ぼろぼろになった体の軽さも。
あれは、紛れもなく本物だった。
では目の前に眠るこの人は、何者か。
「……」
「おっと。乱暴はよしてくれ。君には洗いざらい全部話す。事情も全部」
殺気を見抜かれていたのだろうか。私がその首に狙いを付けるより早く、彼女は振り向いた。
「もちろん、これは人間じゃない。マスター君の素体に、記憶と記録を移し替えたモノ。うーん。精々よく似たそっくりさん、ってところかな」
仮にもマスターと姿形が同じだというのに『これ』と呼ばれることに強い嫌悪が湧いた。
あくまで贋作だ。扱いとしては間違ってはいないのだろう。それでも、物のように言われるのは耐え難い。たとえ揺るぎない事実であるとしても。
「マスターの死を想定し、それでも『カルデアのマスター』というコンテンツを永続させる。本当はその手段自体の用意は以前からあったんだよ。カルデアの善き人々はそれを是とはしなかったし、技術的には机上の空論でしかなかったけどね」
剥き出しの白い肩をそっとダ・ヴィンチが撫でる。愛おしむような、憐れむような手つきだった。
彼女自身も第二次グランドオーダー発令に備え、鋳造された人工英霊だ。
同じく作られた存在となってしまったマスターに対して、何か思う所があるのだろうか。
「何より、マスター君が死んだのなら仕方ないと、諦める潔さが当時はまだ、あった」
けれど、と痛みを堪えるように彼女は目を閉じる。
「もう、事情が違う……我々はもう歩みを止めることは許されない。一度、世界を救ってしまったのだから」
「……だからと言って、こんなことが許されるものか」
声は情けなくも震えていた。手術台の上、なにも知らず眠り続けるマスターの姿。
素体は一体だけのはずがない。このマスターの機能が停止すれば、また新たな素体が用意され、記憶と記録を移し替え起動するのだろう。その次も、次も。何度でも。
例えどれほど苦しみ抜いた末に死を迎えても。諦観の末に死を受け入れたとしても。
世界を、本当に救う日まで。
「この人を、マスターを永遠に物のように使役するなどと。私が許容すると思ったか、レオナルド・ダ・ヴィンチ!」
畢竟、ノウム・カルデアはあなたから死と言う安寧すら奪ってしまった。
激昂のままに手の内に神弓を呼び出す。燃える鏃の先が自らに向けられても、ダ・ヴィンチは動じることなく微笑んだ。
「その通り。度し難い外道だ。許し難い非道だ。……けれど、アルジュナ。これはマスター君自身も了承済みなんだ」
「……痴れ言を!」
「本当さ。我々は冷酷かもしれないけど、残酷じゃない。この計画には流石に本人の意志と同意を求めたよ」
弦を握る手が震える。そんなはずがない。
こんな非道に耐えることを。自分と言う生命への侮辱を、あの人が許すはずがない。
あの人はそんな人ではない。人間を辞めてしまう事を受け入れるはずがない。
……そう、信じたかった。
「それに、マスターは頷いたというのか」
「拍子抜けするくらいあっさりね。『カルデアのマスター』であり続けることを受け入れた。……もし自分が死んでしまったら、託された希望も手折ってきた夢も。背負ってきた異聞帯(せかい)が全部無駄になる。そのくらいだったら、ってさ」
手の震えが大きくなる。ダ・ヴィンチの言葉には虚飾の色はなく、淡々と事実のみを述べているように思えた。
つまりこれは、あの人の意志の結果。
ならば、私は矢を放てない。
胸の内に荒れ狂う衝動のまま、ダ・ヴィンチを殺すことなど造作もない。私の矢は真直ぐに飛び、彼女の首を弾き落とすだろう。
けれど同時にあの人の決意を踏み躙ることになる。
躊躇いが現れたのだろうか。最早形を保つことができず、神弓は光の粒子となって私の手から掻き消えた。
「マスター……どうして、あなたは……」
疑問が口から零れた。
分かっていた。あの人は、きっと言うだろう。そうなったら仕方ないか、と。
なんでもないことのようにへらりと笑って、すべて受け入れてしまうだろう。皆のために。私のために。世界のために。
そんな惨い選択まで強いる世界が異常なのに。何故あなたは当然だと笑って歩み続けようとした!
どうして私に縋ってくれなかった!
「その時に課された条件は二つ。……ひとつ。マシュ・キリエライトには何も知らせないこと」
帰還したマシュ・キリエライトの治療に、わざわざシオンが当たる理由が何となく知れた。記憶処理を行うのだ。
恐らく彼女は今日、マスターの原典が死んだことを永遠に忘れるのだろう。
代わりに戻ったマスターの贋作に対して、彼女はいつものように、先輩と微笑みかけ、他愛のない会話を普段通りに楽しむのだろう。
相手がすでに模造品と化していることも知らずに。
薄ら寒い気分になる。事情を知る者にとってこれ以上陰惨な光景はあるまい。
「ふたつ。自分の死を目にしたサーヴァントには、全て知らせること」
「それで、私に?」
「マスター君との同行率を見る限り、もしも事が起こるとしたら君じゃないかな、とは思ってたけどね」
それから笑った。まさか君自身が慈悲の一撃を与えるとは思ってなかったけど、と。
「そう言えば、まだ理由を聞いてなかったね。何故だい?」
「……」
「確かに致命的な傷だった。即死状態だったのを、礼装の効果でごまかしてるようなものだった。けど、まだ一縷の望みはあったはず。少なくともこっちに戻れば蘇生の目があった」
静かな弾劾が私を抉る。
私は自らの掌を見つめた。先ほどまで生暖かな、あの人の血で濡れていた手を。
エーテルで編まれた身体には、既に血など残っていない。それでも白い手袋の上に、赤い染みがじわじわと広がる幻影を見た。
「何故、君は即刻帰還せずに、一番の信を置くマスターを自らの手で殺す道を選んだのか」
「……それ、は」
乞われたからだ、と叫びたかった。あの人の目が何よりも雄弁に「殺してほしい」と訴えていたからだ。
けれど、どれほど辛くとも、無様であっても。あの人は最期まで足掻かなければならない。
人類最後のマスターだから。汎人類史を背負う者だから。あの人は、諦めることは許されない。
そう、サーヴァントとしての私は理解していた。
なのに人としての私は、マスターの苦しみを終わらせたいと思ってしまった。
あの瞬間。全てが終わり、安らかな眠りに付きたいと願うあの人の魂を呼び戻してまで、この世界に救う価値があるのか分からなくなった。
「……笑ってください、ダ・ヴィンチ。私、マスターの喉を裂いたとき、これで救われると思ったのです。人理を背負う地獄から!」
けれど違った。結局私の行為は、マスターの魂を更なる牢獄の中に閉じ込めただけだった。幾らでも替えの効く肉体と言う名の牢獄の中に。永遠に続く煉獄の中に。
マスターの身体と魂は、あの人一人のモノではない。
私はそう知っていた。……ただ、上面で知っていただけだった。
あの人を構成していたすべては、とっくにフィニス・カルデアの所有物になってしまった。
「こんな、こうなると……知っていたなら。私、私はあの人を……」
無理矢理でも生かすべきだった。
表面上は何も変わることはない。マスターと同じ顔が、同じように笑って、同じように私を頼り、同じように私の名前を呼ぶ。
けれど、それはもうあのマスターではない。限りなく同一に近く、故にあまりにもかけ離れている。
「サーヴァントとしての活動に支障があるなら、マシュと一緒に、記憶処理を受けるかい?」
「……いいえ」
提案に首を振るう。私まであの人のことを忘れてしまったら、あまりにも救われない。
これは、きっと罰なのだ。安易な死を与えた私への。
あなたが使い潰され、擦り切れていく様を最期まで見届ける事こそが。
そうして、マスターは再起動された。
同じ記憶、同じ記録を持ちながら決して同一ではないそれは、事情を知る者たちの懸念を余所に、すぐ『カルデアのマスター』として溶け込んだ。
魔力パスが切れたはずなのに、再び繋がったことに疑問を抱いたサーヴァントも当然居た。勘のいい者は、それが口に出すことさえ憚られる方法によるものだとすぐに悟った。
善性を持つサーヴァントの中にはその外法を認められず、ノウム・カルデアを去った者も居る。
私は、私だけはあの人の傍を離れるわけにはいかなかった。マスターの世界を救いたいという遺志の果てを見守らなければならなかった。
平静に、以前と変わらないよう振舞った。
最高のサーヴァントとして、救うことができなかったあの人の代わりに忠実に尽した。
十分なリソースが用意できなかったため、あの複製体の耐用年数はかなり短い。その代りに、寿命が訪れたら、穏やかに引き継ぎが行われるのだと聞いた。
だから日々、何事も起こらなければいいと願っていた。
もし再び、あの時と同様の事態となったら。
もう一度マスターを殺めなければならなくなったら。……私は、本当に正気のままでいられるだろうか。
恐れていた時は、すぐに訪れた。
マスターはは、私の目の前で腹を半ば食い千切られた。同じ記憶と記録を持っていたのが逆に災いした。……あの人の再現体でなかったなら、サーヴァントを庇おうなどと思わなかったはずだ。
分かっていながら、私はまた守れなかった。
歯噛みしながら、キメラの頭部に狙いを定め矢を打ち込む。怒りの籠った一矢は着弾と同時に大穴を開け、獣の身体を血飛沫と肉片に変えた。
「マスター」
崩れ落ちた身体を支える。
痛みに強張る顔からはみるみる色が失われていった。傷口があまりに大きすぎて、礼装の機能が追いついていない。
楽観的に考えるのは無理だ。これは、助かるはずがない。
それでもせめてあの時と同じ轍は踏むまいと、生暖かな血が流れ続ける傷に手を添えた。
「……大丈夫です。すぐカルデアに戻りましょう。まだきっと……」
「アルジュナ」
あの人は、口の端から血の塊を吐き出しながら笑っていた。状況とは不似合いな表情に、悪寒が走る。
「お願い」
その次に続くであろう言葉を、私は嫌と言うほど知っている。
「殺して」
マスター。かつて、私は同じ言葉を聞きました。
あなたの原典たる人間を同じように殺しました。喉を裂きました。ただ苦痛から助けたかった、それだけでした。
結果、あなたの魂は永遠にカルデアに囚われてしまいました。あなたにとって死は終着ではなく、円環の中の一つになりました。
私はあなたが人でなくなる、最後のひと押しをしてしまいました。善かれと思って、あなたの在り方を歪めてしまいました。
あなたが今、こうして死の苦痛という辛酸を再び舐めることになったのは、私のせいなのです。
負った罪科を全て吐き出しそうになるのをどうにか留め、あの人の手を握りしめる。
「……嫌だ。できない。私には、無理だ」
「アルジュナ」
あの日と同じ、どこまでも透明な目が私を見た。浮かんだ涙が一筋、血に汚れたこめかみへ流れていく。
「おねが、い」
ごめんなさい。痛い。苦しい。辛い。もう歩けない。頑張れない。だから、せめて最期くらい楽になりたい。
今まで必死に隠してきたであろう弱音が、か細い声と共に漏れた。
記憶と記録を同期してある以上、それはあの人がずっと抱えていた痛みと同義だ。
ああ。その声を聴いてまで、私はあなたを『カルデアのマスター』としてあれ、と鼓舞することなどできはしない。
「……。……分かり、ました」
覚悟を決める。
短剣を引き抜いた。弱弱しく呼吸を繰り返し上下する、その喉笛に刃を置く。奇妙なほど懐かしい心地になる。
二度目だ。本当に世界を取り戻すまで、私は何度マスターの死を見送るのだろう。
「あのさ、アルジュナ」
すうっと目が細められる。血に汚れた口の端がぎこちなく動いて、微笑みの形を作る。
「……はじめてだから、やさしくしてね?」
「……。ふ、ふふ」
こんな状況で言うにしてはとても性質の悪い冗談だ。一瞬虚を突かれて、馬鹿らしさに久しぶりに笑って、それから。
「おやすみなさい、マスター」
私はあの人の喉を再び裂いた。
迸る血を抑えることもしなかった。生温い赤が服に染み入り、肌を汚していくのを私はぼんやりと感じていた。
きっと今の私には、白など似合うはずもない。血濡れた姿が相応しい。
あの人の目から光が消え、虚ろになるまで、私は決して目を逸らさなかった。泡となって零れ落ちようとする最期の吐息を拭って、目蓋を伏せる。
どうか、束の間の夢をマスター。またカルデアで逢いましょう。
「……アル、ジュナさん?」
硬い声に顔を上げる。マシュ・キリエライトだった。赤く染まった私の姿と、腕の中のマスターの亡骸を認めて、ひっと喉奥に言葉を詰まらせる。
「どうして」
マスター殺しの場面を目の当たりにするのは、強い衝撃があったらしい。盾に縋る余裕もなく、その場に座り込んでしまった。
「どうして、マスターを、」
彼女は本当に覚えていないのだ。本物のあの人はとっくに死んでいることも。私の腕の中で事切れているマスターは、複製であるということも。
そしてきっと、今日のマスターの死も記憶から拭われてしまう。ほんの少しだけ彼女を哀れに思った。
「説明は後です。マシュ・キリエライト」
壊れ物を扱うように、私は恭しくあの人の身体を抱える。
死体を置いていくわけにはいかない。その死の直前までの記録も次の『カルデアのマスター』に同期させなければ、周囲との齟齬が生まれてしまう。
そう、この人の存在は、最後の最期まで利用され尽される。カルデアのために。人理のために。守りたかった世界のために。
「早く、カルデアに帰還しましょう。きっと、全てがただの悪い夢なのですから」
私が狂気の淵に居るように映ったのだろうか。こちらを見上げるマシュ・キリエライトの表情は怯えていた。
ひとり。
あの人は、もう唯一のマスターではない。『カルデアのマスター』はいくらでも代替がある。
つまり、以前のように丁重に扱う必要も、丁寧にケアを行う必要もない。
やろうと思えばできた。皆が知ってはいた。しかし最後の倫理の壁が辛うじて、マスターを使い潰すことに反対していた。
人造ではあるが、尊重すべきヒトだと認識していた。
また、ひとり。
あの日。私が再びあの人を殺めた日。再起動され、何でもなかったようにけろりとして戻ってきたマスターを見て、誰もが思ったはずだ。
――ああ。使えるモノなんだ、と。
だから、マスターの命の価値はとても軽くなった。
世界を取り戻すための旅路は決して平坦な道ではない。危険は徐々に増していき、それに従い私があの人を看取り、慈悲を与える機会も増えた。
ひとり。
積み上がる屍の果て、あの人が人を辞めてまで、取り戻したかった世界があると信じて。
また、ひとり。
殺めた数が両手の指よりも多くなった頃には、感情は枯れ果てた。逡巡や感慨もなく、一連の作業であるかのように殺した。
とても、懐かしい気分だ。
生前の私も、ただこの悲惨な戦争を終わらせたい一心で己を殺し、ただの機械のように動き続けていたのではなかったか。
こんなのは嫌だと嘆き、悲しみ、理不尽に怒る感情を、悪だと切り捨て封じ込めて。
……それは誰にでもあることだと私に説いてくれた、たった一人のマスターは、もういない。
戻ってくることは、ない。
私の暗闇が照らされることは、もう、ない。
スレ「」ですがそうです 覚えていて頂いて嬉しい
貴女のくらいだとまた違うんだろうが…
最後の最後まで記憶が続いてる人形と違ってコレは記憶が改竄されてるのが逆にダメよね
同意した記憶もそのままに連続させた方がリスク少なそうだよね…
心が擦り切れるかどうかの博打は元々やってるようなもんだし
信じがたいことにあっさり死ぬ
というのはどうかな
なんですぐ曇らせの英雄にされてしまうん?
でもぐだが望んだ事だし
世界と個人を秤にかけて後者を選べるタイプだよね
エドモン以外のアヴェンジャーとかエレちゃん閻魔ちゃん玉藻あたりの魂に惚れ込んでる勢かなぁ
あとパイセン
閻魔亭は大好きなお話だけどあれでそんな仄暗い妄想がこんこんと湧くようになった
あの頃はギリギリ経験も信頼も足りなかったかもだが今はもうそれもないし…
傷付けるどころじゃない
オリジナルの遺体は姪がこっそり持ち去っていてもおかしくないな
死者が生者に力を貸すからギリギリ道理が通るのであって死者が死者の夢に寄り添ってしまうのはもう何一つ道理が残らない
こうして死者に生者の影を妄執的に重ねる鯖だけが残った
生死の重要さを理解してても絆を繋いだ相手の遺志を無碍にできない人多そうだしな…
よってアルジュナを念入りに曇らせ似たような奴らは残ると示唆する
自分の顔を見たマスターを殺せてよかったね…
これ既に幕間2通過後だろうから地獄では…
むしろ次の自分が必ずやとか絶対思い出す
本人にコピーあるって事知らせたらますます自分を大事にしなくなりそう
カルナはむしろ思う所あってもそれがマスターの最後の意志ならって従うタイプじゃねーかな…
それこそ新所長でもレイシフトとマスター適性は揃ってる訳だし…
知らず知らず誘導されてるんじゃないか案件ってこれじゃないかとたまに考える
誰もかれも苦悩し出すよね
そもそも稼働時間短いコピー体に装填出来るだけの運命力あるのかな…
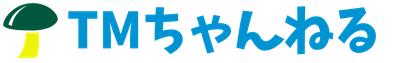



やっぱり秦建てるわ