「そうなんだ。どうりで美味しいと思ったよ」
「いかがです。このクッキーも、私が作ってみたんです。あなたが喜ぶかと思って」
「うん、これも美味しい。流石、アルジュナは何でもできるなあ」
「……本当に、美味しいですか?」
「うん。君は本当に、最高のサーヴァントだね」
「……。マスター」
「うん?」
「あなたは、今、幸福でしょうか」
「……。急におかしなことを聞くんだね。もちろん。とても幸せだよ」
「……。そうですか。それなら、いいんです」
きっとあなたの目前には、純白な自明。恍惚の世界が広がっているのだろう。
だからこそ、こう述べる行いを許してほしい。あなたの魂に安らぎあれ、と。
差し出された資料を見る。聞き取りを行ったマスターの行動レポートだろう。
起床してから帰還するまでのほぼ丸一日に渡って白紙。つまり今日一日の行動に覚えがないということだ。
「この記述を信じるなら、マスター君は無意識の内に、特異点の修復を終わらせたってことになる」
「……特に問題点は見られませんでしたが」
もちろんその特異点には私も同行していた。
マスターからの指示は完璧で、『カルデアのマスター』として求められている行動そのものだったように思える。
「最初に起動した『カルデアのマスター』から、記憶に穴はあったけどさ。それにしたって、これは大きすぎる」
「……。素体の期限が近い、というのも一因なのでは」
「それはない。身体はともかく、頭の部分はちゃんと作り込んであるさ。
今、マスター君の身体で最も大切なのは、今までの記録と記憶の詰まった脳髄だ」
ダ・ヴィンチの言葉にわずかに嫌悪の表情を返す。最早覆らない事実ではあるものの、マスターが物として扱われる感覚には未だに慣れない。
まだ我々は世界を救えていない。『カルデアのマスター』が世界に必要とされる限り、フィニス・カルデアの所有物となったあの人の安寧の眠りは遥かに遠い。
「懸案事項として調べておくよ。今まで蓄積されていく経験の方にばかり目を向けてたからね。
零れ落ちていくもの。マスター君が何を失っているのかは、誰も気に留めていなかった」
私は乾いた笑みを浮かべた。
喪失。自分の肉体の所有権も、死の安息も失ったあの人から、これ以上何を奪えるというのだろう。
「驚きだ。既にあらゆるものが、マスターから剥奪されたと思っていましたが」
「君に皮肉は似合わないぞアルジュナ。それはホームズの仕事だろう?」
ダ・ヴィンチは涼しく言葉の棘を受け流し、
「聞き取りは以上だ。ご苦労様」
どうやら今回の『カルデアのマスター』は、引き継ぎの形式で終了できそうだね、とダ・ヴィンチは微笑む。
どうあれ我々は共犯者だ。声高に批判することなどできはしない。
戦場においては私が、カルデアにおいては彼女が。マスターの死を看取るのだから。
「取るに足らないことです。……それより、随分と賑やかですね」
「お茶会だから。まあ、自分しかいないけど」
たっぷりの色濃い紅茶。自分で作ったらしい質素な菓子類。狭い机の上は確かに、ちょっとした茶会の様相だ。
「何故一人、それも自室で?」
食堂なら、相手になるサーヴァントも大勢居る。問いにあの人は物憂げにカップの表面を見つめ、
「もちろん、みんなで一緒ってのも楽しいけどさ。たまに一人になりたい時もあるから。……あれ。これって『カルデアのマスター』らしくないのかな」
『カルデアのマスター』。耳に慣れてしまった単語に一瞬動揺するが、私は平静を装う。
マスターの言葉は概念としてのそれではなく、ただ自分らしさという意味合いだろう。
連綿と綴られる『カルデアのマスター』という概念。
自らの足元に同じ顔の屍が無数に重なり、いずれ自分もそこに朽ち果てる定めだと、一切知らないはずなのだから。
「いいえ。とても、『あなた』らしいと思います」
それから尋ねた。もしかして私お邪魔でしょうか、と。
「全然。ほら、君も座って。せっかくだし二人で一緒にお茶を飲もう」
口直しに、と摘まんだ菓子は甘すぎる。この紅茶と合わせたら、歪ながらも均衡が取れているのかもしれない。
なので、総合的に鑑みた場合。
「美味しいですね、マスター」
「……絶対に嘘だよね、それ」
気を遣わなくったっていい、とむくれたあの人は紅茶を啜る。私は笑う。まだ笑うことができたのか、と自分を嗤う。
二人だけのお茶会は静かに、穏やかに続いていた。
「あのさアルジュナ。……私って、本当にわたしかな」
唐突にそう尋ねられて、私はついあの人の顔を真直ぐ見てしまった。認識阻害により、曖昧にしか捉えられなくなった顔を。
「時々、来るんだ。ふっと真っ白で心地いい世界に包まれる時間が。
ああ、しあわせだなあ、って夢見てるみたいにぼーってしてさ。
気が付いたら私、自然にマシュとお喋りしてるの。今日のご飯のこととか、明日のトレーニングの話とか。
なんにも意識してないのに、舌はぺらぺら動いてるし頭は話題を選んで喋ってる。
不安になって、今日の私、どうだった? って聞いても普通でしたよ、って不思議そうな顔で答えるの」
……怖い。怖いよアルジュナ。私は怖い。
私って自我が居なくても、この身体は勝手に動くの? 私らしい行動をできるの?
だったら、このいま、世界を感じている私なんか要らないじゃないか。
真っ白な間、私の心はなんにも分からなくなるのに、わたしの身体だけが平然と続いていく。
だから私が居なくなったことに、誰も気付かない。ねえ。そんなことってあり得るの?」
いいえ。そう答えようとしてダ・ヴィンチの言葉を思い出す。徐々に広がる記憶の穴。
恐らく、今日の微小特異点での状態も同じだったのだろう。自我が無くとも、無意識のうちに全てを十全に行えるようになったのだ。
『カルデアのマスター』として取るべき行動を。なんの意思も思考も介さず、一つの機構として。
怖気がした。それは、一種の抜け殻ではないのか。本当にあの人と同一と呼べるのか。
我々が続けてしまった、『カルデアのマスター』という形骸でしかないのではないか。
激しく咳き込む。白い机に、床に、カップに。血の飛沫が鮮やかに散らばる。
近づいて、背中を擦る。服越しですら分かる痩せ衰えた身体。この素体も期限が近い。
嫌な予感があった。最早意識は不要となり、記憶の穴は移し替える度に進行していく。
ならば、次の『カルデアのマスター』に、意識は、自我は発生するのだろうか。
例え消えてしまったとしても、誰にもそれは判断できない。意識あるように振舞う無意識と本当の意識の判別など、他者には不可能だ。
内面を失った虚無のまま、『カルデアのマスター』は続いていく。誰に気付かれることもなく。
それがやがてあの人が至る極点。成れの果て。
「ごめんね、変なこと聞いて。最近具合悪いから、悪いことばっかり考えるのかも」
ダ・ヴィンチちゃんの薬、飲んでるのにね。口元の赤を弱々しく拭って、あの人は微笑んだ。
「ねえ、アルジュナ。また、もう一度お茶会をしようよ。
今度は君に、紅茶とお菓子作ってもらうから。忘れないで。約束だよ」
私は虚ろに呟いた。ええ、きっと。
蓄積されていく『カルデアのマスター』の経験と反し、不要とされ徐々に削ぎ落とされていったのは、意識。
つまり死して尚、情報を転写し続けていくうちに、『カルデアのマスター』であることを極めてしまった訳だ。
意識、意志、自我。そういった物に決めてもらわなくても、マスター君は十分に『カルデアのマスター』として振舞える」
ラボのベッドには、同じ顔が二つ。肉体の期限の迫る、前任者と呼ぶべきマスターと次の『カルデアのマスター』。引継ぎ作業の真っ最中だ。
「次のマスターに、意識は宿りますか」
「……いいや。恐らくは、完全に消失する」
残忍な事を言った自覚はあったのか、少女は瞑目する。
擦り切れ、今まさに消え逝こうとしている、マスターの人間の意識に祈るように。
「しかし、意外だよ。君はどんな手段を用いてでも、この引継ぎを止めると思っていた。
私自身、もうこれ以上は無理だと思ったから」
目に見えて疲労の色が浮かぶ少女に私は微笑んだ。
あなたが言ったのだ、ダ・ヴィンチ。我々は、歩みを止めることは許されない、と。
「……。ああ、そうか。そうだった」
残酷なことだ、と少女は呟く。
「マスター。その紅茶、私が淹れたんです」
あなたはこの紅茶の熱も、香りも感じてはいない。
「いかがです。このクッキーも、私が作ってみたんです。あなたが喜ぶかと思って」
あなたは味も、喜びも感じていない。
『カルデアのマスター』として脳髄に刻み込まれたアルゴリズムに従い、まるで感じているかのように振舞うだけだ。
「……本当に、美味しいですか?」
だから、あなたがどのような返事をしたとして、あるのは受け取る側の感傷でしかない。
あなたが「思う」のも「感じる」のも、全て機構としての返答であり、まやかしだ。言葉以上の意味はない。
そう、分かっていても。
「……。マスター」
どうしても、私は尋ねずにはいられなかった。
「あなたは、今、幸福でしょうか」
この人は感じることなんてできはしない。存在するのは、かつてマスターが語っていた、真っ白で心地よい世界だけ。
だから今までずっと抱えてきた痛みも、悲しみも、苦しみも、遠いものになった。
内面はなく、苦痛を受け取る『私』が存在しないからだ。
あなたの目前にあるのは、純白なる自明。選択も決断も必要としない、ただあるべきことを、あるべきように行うシステム。
迷いを排した……いや、廃した機構だ。
あなたが行き付いたこの状態を一種、救いだと思うのは、少々独善が過ぎるのだろうか。
だからこそ、こう祈ることを許してほしい。あなたの意識に安らぎあれ、と。
オルジュナが美しいと言ってくれた在り方は喪われちゃったんだな…
わるいノウム・カルデアと擦り切れるマスターの意識と曇るアルジュナの話です
お茶会をもう一度
またお茶会しようねって言ってくれた本人はもう覚えてないんだ…
だが、彼女だけにはそれが許される。……いや、許されるような気がする
朕はノリをひくため準備してそう
まぁ死んじゃってるから知る由もないんだが…
多分バグのように異なる選択が増え始めて新しい自我が成立するんじゃないかな
元のマスターに想い入れある面子と揉めたり色々拗れた展開になるやつ
そして古くからの仲間が見てるのは私じゃなくて前の私だ…って気づくんだね
カルデアのマスターのエミュは出来ても元の家族の娘はエミュれないんだね…
一章のぬが英雄としてのジャンヌの反転エミュでしかないのと似てる?
稼働時間短いしメンテもいるだろうから家族の所に帰るどころじゃないしそもそも本人じゃない
全部終わったら今度こそ永遠の眠りにつくだけとか虚しすぎる…
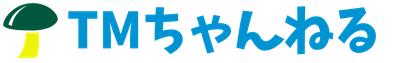



ゲッター艦隊かな?