非現実的な光景だった。ゲームや漫画の中で見慣れた竜が今まさに眼前に舞っている。
ドクターが先程申し訳なさそうに叫んだところによると、あれはワイバーンという名前らしい。
低く唸り、牙を剥き出し、今にもこっちに襲い掛かろうとしている。
そんな危機的な状況の中で自分が考えた事と言えば、あの手羽元、美味しそうだなあ、だった。
やっぱりさっぱり煮かな。でも洋風なのも捨てがたい。かりっとした唐揚げでもいいなあ。
カルデアに食肉なんてない。すっかり縁遠くなってしまっていたから、想像が止まらなくなった。ついでによだれも止まらない。
なんでもいい。お肉が食べたい。忘れられがちだが、自分は健全な育ち盛りなのだ。例え完全栄養食であろうが、レーションは物足りなさすぎる。
マシュの呼び掛けにやっと我に返った。目の前の手羽元が、鱗びっしりの爬虫類だと現実を知る。
全く美味しそうには見えなくって動揺する。けれども相手には、自分は美味しそうに見えたらしい。大きく口を開けてこっちに向かってくる。
がちん。一瞬前まで自分の頭があったところに、ワイバーンの牙が合わさっていた。
サーヴァントの誰かが、襟首を引っ掴んでくれたんだろう。お陰で生き残れた。
戦場でぼうっとするなんて、きっとお腹が空いてるからだ。フランスの青い空に空に浮かんだ、光の帯を仰ぎ見て納得する。
それから決めた。このワイバーンを倒して、食べよう。糧としよう。相対した者の当然の権利として。美味しく、感謝を込めて。
生か死か。食うか食われるか。戦いの場には常にそれしかない。
倫理が怖くて人理は救えない。腹が減っては戦はできぬ。ならば自分が為すべきことは一つだけ。
「……よし、やろうマシュ!」
ワニは鶏肉の味と聞いたことはあるけれど、ワイバーンだって同じなのだろうか。
お皿の上に載った、尻尾肉のステーキをじっと見つめる。分厚い一枚肉に切ったのはゲオルギウス。「汝は竜!」と力強く一刀両断してくれた。
見てくれはふつうの肉だ。フォークを刺し、持ち上げる。ぼたぼた滴る肉汁と炙られた肉の匂いが、食欲をうずかせる。
一口、行ってみた。
「…………」
すごく、硬い。よく噛んでもいつまでも塊のままに残り続けている。けれど、確かに肉だ。一噛みごとに口の中にじゅうっと溢れるエキスを飲み干すと、最高に生きていると感じられる。
不思議な心地だった。さっきまで生きていて、自分を食べようとしていたワイバーンを食べている。食物連鎖の頂点に立っている。
「いかがですか、先輩」
マシュが支給のレーションを齧りながら覗き込んできた。返事の代わりにフォークを差しだす。
「食べてみる?」
「ですが、これは先輩の分ですし、それにワイバーンの……」
「美味しいよ。これぞお肉って味がする」
「……硬い。硬いです、先輩」
「分かる」
「あっ、でも肉汁が……これは、美味しいですね」
「でしょ」
マシュがほんのり頬を染めて笑う。さっきまで盾を持って、ワイバーンの胴を力強くぶん殴っていたとは思えないくらい可愛い笑顔だ。
「カルデアに持って帰ろう。久しぶりの肉だし、みんな喜ぶよね、きっと」
「はい。スタッフの皆さんも、ひもじい思いをしていたでしょうから」
焚火の向こうを見た。サーヴァントたちが思い思いに尻尾肉のステーキを味わっている。かぶりつきながら、時代も歴史も出自も違う英雄たちが語り合っている。
サーヴァントは影法師。基本的に食事は必要ないと説明されたけれど、やっぱりみんなで囲む食卓は気持ちも安らぎ会話も弾む。
もっと、仲良くなれるかもしれない。
「そうですね」
「全部終わったら、絶対にやろうよ。スタッフの皆と、ダ・ヴィンチちゃんと、あとドクターも誘って」
食は生者の特権だ。しかし人理の歪む今、死者の影も二度目の生を謳歌し、喰らう。
生と死の境界はいつでも曖昧で、気を抜けば呑み込まれてしまう。常在戦場。腹だって常に満たしておくべきなのだ。
カルデア飯。ああカルデア飯。
フランスでワイバーンの尻尾ステーキを食べる話
エリちゃんの尻尾かぁ…イケそう!
尻尾生えてるサーヴァントわりといるから食べ比べ出来るね
ホムンクルスの目ん玉をしゃぶるぐだ子とかにならない?
ケルト兵とかチンピラが
適切な調理法を見つけてベディにも教えてあげよう
ってことはその根元にはしっかりと鳥の筋肉が備わってるんだよね
全然関係ないけどメディアさんは手羽元って食べたことある?
ドクターの目は死ぬ
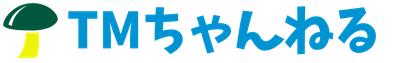



ハンティングクエストってそういう……